更新日:2025年8月27日
栄養バランスの良い食事とは?ポイントや無理なく続けるための工夫を紹介

栄養バランスの良い食事は、健康や活力を維持する上で欠かせません。栄養バランスが崩れると、疲れやだるさを感じるようになったり、免疫機能が低下したりすることも。しかし、仕事や育児などで忙しく、栄養バランスの良い食事を続けるのは難しいという人も多いのではないでしょうか。この記事では、人の体に欠かせない「五大栄養素」の役割や、栄養バランスを良くするポイントについて紹介。無理なく続けるための工夫も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

監修
福渡 努 先生
滋賀県立大学 人間文化学研究院 教授/日本ビタミン学会 理事/ビタミンB研究委員会 副委員長
INDEX
栄養バランスの良い食事とは?
栄養バランスの良い食事とは、主食・主菜・副菜を基本に、五大栄養素(炭水化物・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラル)を過不足なく摂り入れた食事のことを指します。
五大栄養素にはそれぞれ役割があり、炭水化物に含まれる糖質と脂質は体を動かすエネルギー源に、タンパク質と脂質は体を作る材料になる栄養素です。ビタミンとミネラルは、体の調子を整える潤滑油のような役割を果たしています。
私たちの体は食事から得た栄養素で成り立っているため、生命活動を維持し、健康的な毎日を送るには、日々の食事から五大栄養素を偏りなく摂ることが大切なのです。
栄養バランスの良い食事に欠かせない「五大栄養素」とは?
「五大栄養素」とは、エネルギー源や体を作るもとになる「三大栄養素(炭水化物・脂質・タンパク質)」に、必要量は微量ながらも発達や代謝機能の維持に必要不可欠な「微量栄養素(ビタミン・ミネラル)」を加えた5つの栄養素のことを指します。微量栄養素のうち、ビタミンは他の栄養素の代謝を助ける働きがあり、ミネラルは体のさまざまな働きに関わっています。
ここからは、五大栄養素についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
・炭水化物
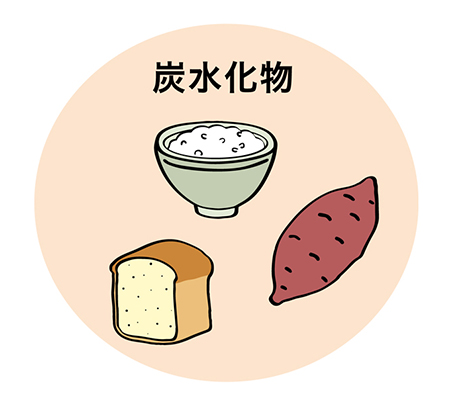
ご飯やパン、サツマイモ、麺類などに多く含まれる炭水化物は、体内でエネルギー源になる「糖質」と、エネルギー源にはならないものの、生活習慣病の予防や腸内環境の改善などに役立つ「食物繊維」に分けられます。
糖質を摂取すると、体内でブドウ糖(グルコース)に消化され、脳や筋肉など全身を動かすためのエネルギーになります。そのため、糖質が不足すると、エネルギーが不足することで、疲れやすくなったり、集中力が低下したりすることも。さらに、肝臓や筋肉などに貯蔵されているグリコーゲンの他、脂肪やタンパク質が分解され、エネルギーとして使われることもあるため、体重減少や筋力低下につながることもあります。
余った糖質は脂肪として蓄えられるため、摂りすぎると肥満の原因になることも。過不足がないよう、自分に合った量を摂ることが大切です。
・脂質

脂質はエネルギー源の1つで、炭水化物・タンパク質の約2倍のカロリーを持つ栄養素です。エネルギー源になるだけでなく、細胞膜を構成する、脂溶性ビタミンの吸収を助ける、ホルモンの材料になるといった重要な役割を担っています。
摂りすぎると、中性脂肪として脂肪組織や肝臓などに貯蔵されるため、肥満や生活習慣病のリスクが高まることも。生命活動には欠かせない栄養素ですが、摂りすぎには注意が必要です。
・タンパク質
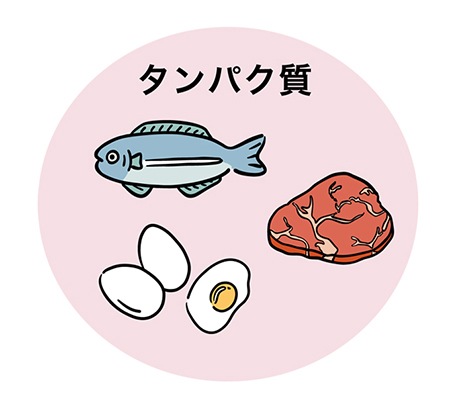
タンパク質は体の組織などを作るもとになる栄養素で、肉や魚、卵、大豆製品、乳製品などに多く含まれています。
摂取したタンパク質は、消化によって一度アミノ酸に分解された後、筋肉や内臓、皮膚、神経などの成分や、ホルモンや酵素、免疫物質などの成分に変わります。そのため、体の組織や機能を維持する上で欠かせません。不足すると、成長障害が起きたり、体力・免疫機能が低下したりする恐れもあります。
ただし、過剰に摂取しすぎると腎臓に負担がかかるといわれているため、腎臓病の人は注意が必要です。
・ビタミン
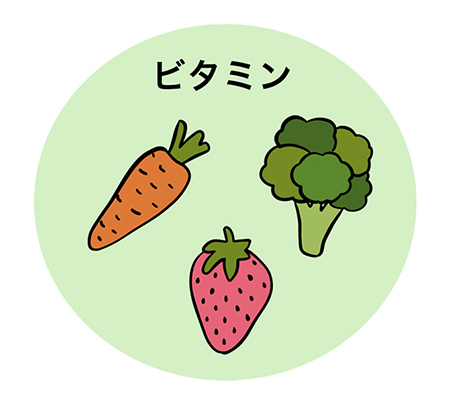
ビタミンはエネルギー源にはなりませんが、体の機能を正常に保つ上で欠かせない栄養素です。
現在知られているビタミンは13種類で、それぞれ水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンに分類されています。水溶性ビタミンは、ビタミンB群(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)とビタミンCの9種類。脂溶性ビタミンは、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンKの4種類です。
なかでもビタミンB群は、糖質や脂質、タンパク質の代謝に関わり、エネルギーを作り出すのに必要な栄養素です。不足すると脳や体がエネルギー不足になり、疲れやだるさが生じることもあるため、注意が必要です。
ビタミンは体内でほとんど合成されないため、食事から摂取する必要があります。特に水溶性ビタミンのビタミンB群とビタミンCは、種類によって含まれる食品が偏っていたり、体から失われやすかったりするため、日々の食事からこまめに補給することが大切です。ビタミンは野菜や果物、きのこ類、肉、魚などさまざまな食品に含まれます。
・ミネラル

ミネラルとは、体の機能に関わるさまざまな無機質のことを指します。例えば、骨や歯の構成成分となるカルシウムやリン、血液中で酸素を運ぶ鉄分、酵素の働きを助ける亜鉛やマグネシウム、体内の水分バランスを調整するナトリウムやカリウムなどが挙げられます。
ミネラルは体内で作り出すことができないため、食品からの摂取が欠かせません。不足すると、骨粗しょう症や筋力低下、貧血などが起きることもあるため、注意が必要です。ただし、過剰摂取は高血圧などの原因になることもあるため、摂りすぎないようにしましょう。
栄養バランスの良い食事にするための4つのポイント

栄養バランスの良い食事を実現するには、まずは1日3食しっかり食べたり、主食・主菜・副菜を揃えたりすることが大切です。ここでは、栄養バランスを整えるために押さえておきたいポイントを4つ紹介します。
自分に必要なエネルギー量を把握する
まずは、自分に必要な1日のエネルギー量を把握しましょう。
必要なエネルギー量は、年齢や性別、普段の活動量によって異なります。バランスの良い食事を心掛けても、必要以上にエネルギーを摂っていると、肥満につながることも。一方、食欲の低下やダイエットなどの影響でエネルギーが不足しすぎると、栄養失調の原因になることもあります。そのため、消費されるカロリーと摂取するカロリーのバランスを見て食事量を調整することが大切です。
成人男性と成人女性の摂取カロリーの目安は下記の通りです。1日を座って過ごしている人は「身体活動量が低い」、座っていることが多いが軽い運動をする人・立ち仕事や習慣的にハードな運動をしている人は「身体活動量が普通以上」の行を確認しましょう。
| 男性 18~69歳 | 男性 70歳以上 | 女性 18~69歳 | 女性 70歳以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 身体活動量が低い | 2,200± 200kcal | 1,400~ 2,000kcal | 1,400~ 2,000kcal | 1,400~ 2,000kcal |
| 身体活動量が 普通以上 | 2,400~ 3,000kcal | 2,200± 200kcal | 2,200± 200kcal | 1,400~ 2,000kcal |
〔出典:農林水産省 実践食育ナビ「食事バランスガイド早分かり」〕
1日3食をしっかり摂る
1日1食や1日2食で済ませていると、エネルギーが不足したり、栄養バランスが偏ったりしやすいので、1日3食きちんと食べるようにしましょう。朝食・昼食・夕食と3回に分けて食事を摂ると、1日に必要なエネルギーや栄養素を無理なく摂取できます。
特に朝食を抜いてしまうと、脳や体のエネルギーが不足して集中力や記憶力が落ちたり、疲れやだるさが生じたりしやすいといわれています。「忙しくて朝ごはんを食べる時間がない」という人も、簡単なものでも良いので朝食を摂る習慣をつけるようにしましょう。
主食・主菜・副菜を揃える
バランスの良い食事を実現するには、主食・主菜・副菜を揃えることが大切です。
主食は、エネルギー源となる炭水化物を含むご飯・パン・麺類など。主菜は、タンパク質を含む肉・魚・卵・大豆製品などを使ったメインのおかずを指します。副菜は、ビタミン・ミネラル・食物繊維などが豊富な野菜やきのこ、海藻などを使った料理のこと。この3つを組み合わせた食事を1日2食以上食べると、栄養バランスが整い、カロリーの摂りすぎも防ぐことができます。
忙しいときは丼ものや麺類などで済ませがちですが、肉・魚などを使った主菜や、具沢山の汁物・サラダなどの副菜を一品でも追加するようにしましょう。
さまざまな食材を組み合わせる
さまざまな食材を組み合わせるのも、バランスの良い食事を実現する上で欠かせないポイントです。1つの食材だけで五大栄養素すべてをまかなうのは難しいため、複数の食材を少しずつ取り入れることで不足しがちな栄養素を補いましょう。
特に取り入れたいのが、豆・ごま・わかめ・野菜・魚・しいたけ・いもの7品目です。この7品目はバランスの良い食事をするために必要な和の食材で、頭文字を取って「まごわやさしい」と呼ばれています。どの食材も低脂質でビタミンやミネラルを多く含んでいるので、生活習慣病の予防にも役立つとされています。
特に外食や中食(コンビニで購入した弁当などを自宅で食べる場合)では、パスタやラーメンなど炭水化物中心の食事になりやすいため、こうした食品を含むメニューを選ぶことが大切です。
栄養バランスの良い食事の献立例

先ほども紹介したように、1日に必要なエネルギー量は、性別や年齢、身体活動量によって異なります。ここでは例として、20代女性と中高年男性の理想の献立例を紹介しますので、献立を考える際の参考にしてみてください。
・20代女性の献立例1)
【朝食】
ご飯普通盛り(主食)、目玉焼き(主菜)、じゃがいものみそ汁(副菜)、ヨーグルト、果物
【昼食】
スパゲッティ(主食・副菜)、サラダ(副菜)、カフェオレ
【夕食】
ご飯普通盛り(主食)、じゃがいもの煮物(副菜)、ほうれん草のおひたし(副菜)、魚の照り焼き(主菜)、納豆(主菜)、果物
・中高年男性の献立例1)
【朝食】
ご飯大盛り(主食)、ひじきの煮物(副菜)、ほうれん草のおひたし(副菜)、納豆(主菜)、牛乳、果物
【昼食】
ご飯大盛り(主食)、さんまの塩焼き(主菜)、きんぴらごぼう(副菜)
【夕食】
ご飯中盛り(主食)、かぼちゃの煮物(副菜)、酢の物(副菜)、焼き鳥(主菜)、果物
1)出典:農林水産省 みんなの食育「バランス良く食べる食事例」
・献立を決める際のポイント
1食ですべての栄養素を摂取するのは難しいので、1日単位で栄養バランスを考えることが大切です。毎食、主食・主菜・副菜をできる限り揃えるようにし、不足している場合は、それ以降の食事で補うようにすると1日のトータルの栄養バランスを整えられます。
基本的には、主菜はほどほどにして、副菜とご飯をしっかり食べるようにしましょう。刺身や煮物、蒸し物など油を使わない料理を選べば、食事量を減らさずにカロリーを抑えることができます。
外食をする際は、副菜の小鉢がついた定食タイプにすると良いでしょう。食後にデザートを食べる場合は、ビタミンやミネラルを豊富に含む果物がおすすめです。
栄養バランスが崩れるとどうなる?

生命活動に必要なエネルギー源やタンパク質、ビタミン、ミネラルなどを十分に摂れない状態になると、いわゆる「栄養失調」のような状態が引き起こされることも。ここでは、栄養バランスが崩れることで現れる主な影響を紹介します。
体重の減少や筋力の低下
食事から摂取するエネルギー源やタンパク質が不足していると、エネルギーを補うために、体内に蓄積されている脂肪や筋肉が分解されてしまいます。そのため、長期間にわたって不足した場合、体重が減少したり、筋力が低下したりすることも。特に加齢や病気、ダイエットなどの影響で食事量が減っている場合は注意が必要です。
疲れやだるさなどの症状
エネルギー源となる栄養素が不足すると、疲れや冷えなどの症状が現れることがあります。
現代では、エネルギーは十分摂取できていても、ビタミンやミネラルなどの栄養素を十分摂取できていないという人も少なくありません。こうした状態は、「新型栄養失調」と呼ばれています。新型栄養失調は、疲れやだるさ、冷え、気分の落ち込みなどの不調の原因になることもあるため、栄養バランスに気を配ることが大切です。
特に、糖質の代謝に必要なビタミンB1が不足すると、日々の活動や疲労回復に必要なエネルギーが十分に生み出されず、疲れやだるさを感じやすくなります。
また、赤血球を作るために欠かせない鉄分が不足すると、貧血になることで疲れを感じやすくなったり、集中力が下がったりすることも。特に主食のみで食事を済ませることが多い人は、ビタミンやミネラルが不足しやすいため、注意が必要です。
- <ビタミンB1を配合し、体がだるいといった疲れに効くアリナミン製品>
免疫機能の低下
エネルギー源となる三大栄養素やビタミン、ミネラルなどが不足すると、免疫機能が低下しやすくなります。
特にビタミンAや亜鉛をはじめとするビタミン・ミネラルは、免疫系の維持に欠かせない栄養素です。不足すると体の防御力が落ちて、風邪や感染症にかかりやすくなります。感染症にかかると、食欲が低下することでさらに栄養バランスが偏り、悪循環に陥ることも。そのため、普段から栄養バランスの良い食事を摂ることで免疫機能を高めておくことが大切です。
栄養バランスの良い食事を続けるには?気軽にできる工夫
栄養バランスの良い食事を摂りたいと思っていても、仕事や家事、育児などで忙しく、食事に気を遣うのが難しいという人も多いのではないでしょうか。
そのような人に向けて、毎日の生活のなかで気軽にできる工夫を3つ紹介します。
冷凍野菜を調理に使う
厚生労働省では、1日の野菜の摂取目標量を350gと定めています。目標量の野菜を摂るために活用したいのが、冷凍野菜です。
冷凍野菜の一番のメリットは、あらかじめ洗浄・カットされているため、洗ったり切ったりする手間を省けること。例えば、冷凍ホウレン草や冷凍ブロッコリーなどをストックしておけば、必要な分を加熱するだけで簡単に副菜を作れます。電子レンジで加熱調理すれば、フライパンや鍋などを用意する必要もありません。料理があまり得意ではないという人でも、手軽に取り入れることができるでしょう。
調理が必要ない栄養豊富な食材を活用する
「忙しくて料理をする暇がない」という場合は、調理不要で栄養豊富な食材を活用するのがおすすめです。
バナナやヨーグルト、牛乳、シリアル、豆腐、サラダチキンなどを食事に取り入れれば、エネルギー源や不足しがちな栄養素を気軽に補給できます。朝食にしたり、普段の食事にプラスしたりするのも良いでしょう。
こうした食品は、コンビニやスーパーですぐに買えるのもうれしいポイント。パッケージに栄養成分表示が記載されているものも多いので、含まれるエネルギー量や栄養素を確認しやすいのもメリットの1つです。
ビタミン剤やサプリメントを活用する
「バランスの良い食事を摂る余裕がない」「食事だけでは補いきれない栄養素がある」という場合は、サプリメントやビタミン剤を活用するのも1つの方法です。
特に栄養不足による疲れやだるさを感じるときは、エネルギー産生や疲労回復に関わるビタミンB群を含むビタミン剤を活用すると良いでしょう。
ただし、ビタミンB1には、食品から摂取しても体内に吸収されにくいという性質があります。そのため、ビタミン剤を活用する場合は、ビタミンB1の弱点を克服し、吸収しやすい形にしたビタミンB1誘導体「フルスルチアミン」を含むビタミン剤が特におすすめです。
- <フルスルチアミンを配合し、肉体疲労時のビタミンB群の補給におすすめのアリナミン製品>
栄養バランスの良い食事を意識して、健康的な毎日を過ごそう

栄養バランスの良い食事は、健康的な毎日を送る上で欠かせません。まずは、主食・主菜・副菜が揃った1日3食の食事を基本とし、五大栄養素を過不足なく取り入れることが大切です。忙しくて余裕がない場合は、冷凍食材や調理不要で食べられる食品などを活用し、無理なく自分のペースで栄養バランスを整えていきましょう。「栄養バランスの良い食事を摂るのが難しい」「栄養不足のせいで疲れやだるさを感じる」という人は、サプリメントやビタミン剤などの活用も考えてみてはいかがでしょうか。
- <参考文献>
- 農林水産省「ちょうどよいバランスの食生活」, 「みんなの食育」, 「実践食育ナビ 食事バランスガイド早分かり」
- 健康長寿ネット
- E-ヘルスネット




