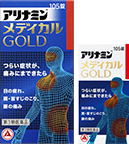更新日:2025年1月30日
腰痛を軽減させる寝方とは?腰痛の原因や腰痛への対処法を解説

腰痛があるとき、どのような寝方をすればよいのでしょうか。腰痛は性別を問わず、日本人が最も多く抱えている不快な症状といわれています。腰痛の主な原因としては筋肉や神経の疲労が挙げられますが、他にも骨の変形、血管や内臓の病気、ストレスなどさまざまな原因がかかわっている可能性もあります。腰痛がひどくなると「痛みがつらくてなかなか寝付けない…」という方もいるのではないでしょうか。今回は、腰痛の原因から、腰痛を軽減させる寝方、腰痛への対処法までを解説します。
監修
竹谷内 康修 先生
竹谷内医院 院長
INDEX
腰痛の原因
まずは腰痛の原因について、解説していきます。腰痛は、筋肉や神経の疲労、脊椎(背骨)の変形、血管や内臓などの病気、あるいは、ストレスなどが原因で起こります。ただし、これらのうちいずれか一つのみが原因ということは少なく、複数の原因が重なり合って痛みを強めていることが多く見受けられます。また、検査でみつかった原因(異常の程度)が、痛みの強さと釣り合わないことも珍しくありません。
腰痛の治療では、異常の程度を確認した上で、痛みが強くつらい場合は、薬で痛みを抑えながら、腰を温めたり、様子をみながらストレッチをしたり、またリハビリのような理学療法などによる対症的な治療を行います。上述の通り腰痛には複数の原因が重なり合っていることが多いため、原因と思われる箇所を手術で修復しても症状があまり改善しないことがあり、このような対症的な処置を行うことも少なくはありません。一方、医学的に緊急性の高い異常、例えば、大動脈瘤※1や腎尿路結石※2による腰痛、あるいは背骨の神経が圧迫されて麻痺が生じている場合などは、痛みの程度にかかわらず手術が必要になります。
※1 大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう):大動脈が「こぶ」のように病的にふくらむ病気。
※2 腎尿路結石(じんにょうろけっせき):腎臓または尿管に硬い固形物状の結石が生じる病気。
寝ているときや寝起きに腰が痛くなる理由とは
睡眠は、体を休めるためにとるものです。ところが腰痛が生じているときは、睡眠時の姿勢が体の負担を増やしてしまうことがあります。朝、目覚めたときに腰に痛みを感じるという場合は、睡眠時の姿勢など、何らかが原因となり、腰に負担をかけている証拠ともいえます。睡眠時の姿勢が腰の負担になり得る理由を挙げてみましょう。
・寝ているときでも腰に体重がかかっている
寝ているときに腰が痛くなる理由の一つとして、たとえ横になった姿勢でも腰に体重がかかっていることが挙げられます。また、腰を守るために柔らかい敷布団やマットレスを使うと、お尻がより沈み込んでしまい、余計に腰に体重が集中してしまうことも。
睡眠中は、無意識に寝返りを繰り返しているものですが、この寝返りには、体重の負荷を分散させるという重要な役割があります。例えば、血流やリンパの流れが滞ったり、神経が圧迫されたりするのを防ぐように働きます。その寝返りが少ないと、体重がかかっている部分の血流やリンパの流れが停滞したり、神経が長時間圧迫されたり、炎症が生じやすくなったりします。腰は寝ているときに最も体重がかかりやすい部位であるため、寝返りが少ないことの影響が生じやすく、それが腰痛につながってしまうことがあります。
なお、柔らかい敷布団やマットレスで寝ることが好ましくないとされる理由には、腰に体重が集中してしまうことの他に、柔らかいと体が沈み込んでしまうため、寝返りをしづらくするということも関係しています。
・睡眠不足が腰痛を招くことも
一方、睡眠時間が短いことや、睡眠の質が低いことが腰痛に関連していることもわかっています。例えば、睡眠時間が短い方には腰痛が多いというデータ※3や、睡眠の満足度が低い方には腰痛が多いといった調査結果※4があります。
睡眠時間や睡眠の質は、さまざまな健康リスクと関連があることが近年注目されていて、腰痛もそれに該当すると考えられています。この関係には、睡眠の質の悪化による炎症反応が関与しているともいわれています。さらに、腰痛のために睡眠が妨げられるという悪循環が生じてしまうこともあります。
※3 房野 絹可.久保 千恵子.尾崎 勝博.後藤 啓輔.田島 直也, 日本腰痛会誌,「当院における腰痛実態調査」, 2007
※4 大友篤,「睡眠の自覚的満足度と腰痛の関係」~仙台卸商研究~, 2015
腰痛と寝方の関係

寝るときの姿勢(寝方)としては、仰向けや横向き、うつ伏せなどが挙げられます。ここでは、それらの寝方と腰痛との関係について見ていきましょう。
仰向け
仰向けの寝方は、股関節が伸びることで腰が反ってしまう傾向にあるため、腰痛によくない寝方とされています。ただし、横向きでは寝られないという方(例えば、肩に怪我をしている方など)の場合は、膝を曲げて立て、仰向けで寝るようにすると、腰への負担をやや軽くすることができます。このとき左右の足のつま先をやや内側に向けると、立てた膝が崩れにくくなり、目覚めてしまう頻度を減らすことができるでしょう。また、膝やふくらはぎの下にクッションを置く方法もおすすめです。
横向き
横向きの寝方は、腰への負担が少なく寝返りもしやすいため、腰痛にはよいとされています。横向きで腰を丸めて一度膝をかかえるようにし、そこから少し戻した状態で寝ると、背骨の血管や神経の圧迫が弱くなるため、おすすめです。
ただし、腰部脊柱管狭窄症※5や腰椎椎間板ヘルニア※6による腰痛の場合、横向きで寝ると足腰に痛み(坐骨神経痛)やしびれが出ることがあるため、注意しましょう。
なお、腰痛があるときに横向きで寝る場合は、腰椎(腰の部分にあたる骨)を支える必要があります。そのためには、腰のくびれ部分に幅10センチ程度に細長く折ったタオルを敷いたり、腹巻きをして、腰の横の部分に小さなタオルを入れ込んだりするとよいでしょう。
※5 腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう):背骨の変形によって、背骨の中を通っている血管や神経が圧迫され、腰痛や足の痛み、しびれなどが生じる病気。
※6 腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア:腰の背骨に加わる衝撃を緩和する役割のある椎間板が加齢などにより変形、断裂することで、腰や臀部、下肢にしびれや痛みが生じる病気。
うつ伏せ
うつ伏せの寝方は、腰椎が反り返った状態になるため、腰痛のある方は避けたほうがよい寝方です。また、首にも負担がかかりやすいといわれています。どうしてもうつ伏せでないと寝られないという場合は、お腹の下にクッションを敷いたりして、腰が反らないよう工夫してみるとよいかもしれません。
ただし、腰が健康な方や柔軟性のある方にとっては、うつ伏せの寝方は特に悪い姿勢ではありません。腰椎椎間板ヘルニアでは、腰を曲げるよりも若干反ったほうが楽な場合もあるため、自分の症状に合わせて試してみましょう。
腰痛のときにしてはいけない寝方はある?
上述のように、仰向けは腰に体重が集中して血管や神経が圧迫されやすく、また寝返りをうちにくいため、反り腰の方や、腰部脊柱管狭窄症などで坐骨神経痛を患っている方は避けたほうがよい寝方といえます。ただし、腰痛の部位や背骨のカーブ、筋肉のつき方などには個人差があるため、最も楽で、かつ寝返りのうちやすい姿勢を自分で探してみるとよいでしょう。
腰痛を軽減させるための寝方の工夫
タオルやクッション、抱き枕を活用する
・腰の下にタオルを敷く
寝ている間に腰にかかる負担を和らげるには、敷布団やマットレスの硬さが重要です。寝返りのうちやすさという点では、あまり柔らかすぎない敷布団やマットレスのほうがよいものの、硬すぎると腰が圧迫されやすくなってしまいます。敷布団やマットレスが硬いと感じるときは、タオルを腰の部分に敷いたり、腰に巻いたりして加減してみるのもよい方法です。
・膝の下にクッションを敷く
仰向けで寝たいが腰への負担が気になる…といったときには、腰への負担を考えて、上述のように膝を少し曲げたり、膝の下にクッションを置いたりして寝るとよいでしょう。その他、横向きで寝るときにも、腰のくびれのあたりにクッションを置くと腰への負担を軽減することができます。
・抱き枕を使う
抱き枕を使うと体重のかかり方が分散され、腰への負担を軽減することができます。また、腰痛の予防に大切な、寝返りをうちやすくなるという点も大きなメリットです。その他にも、抱き枕を使うことで不安が解消されて睡眠が深まり、ストレスの軽減も期待できるともいわれています。それにより睡眠の質が改善され、腰痛の予防や改善にもつながる可能性があります。
寝返りや起き上がり方に注意する
寝返りをうつときや、朝に目が覚めて起き上がるときに力任せに起き上がろうとすると、腰に思わぬ負担がかかることがあります。上半身と下半身がばらばらに動いてしまうと、そのような負担がかかりやすくなるといわれています。
対策として、腹筋に少し力を入れることで、上半身と下半身が同時に動くようになり、腰への負担を減らすことが期待できます。また、ゆっくりと体を動かすように心がけることも効果的です。
腰に負担がかかりにくい寝具を選ぶ
・敷布団やマットレスの硬さと寝返りのうちやすさをチェック
腰痛の原因の一つとして、寝具が体に合っていないことも挙げられます。寝具にこだわってみるのも腰痛を軽減させるための一つの手でしょう。上述のように、敷布団やマットレスは柔らかい方が快適に感じることがあるものの、柔らかすぎると腰が沈んで体重がかかりやすくなったり、寝返りをうちづらくなったりすることで腰に負担をかけてしまうことがあります。そのため、敷布団やマットレスはどちらかといえば硬めのほうがおすすめです。
もし、新しく寝具を買うのであれば、実際に寝転がってみて、硬さや寝返りのうちやすさの確認をしてから選ぶようにしましょう。とはいえ、寝具を買い替える機会は通常そう頻繁にはないはず。すぐにできる対策としては、タオルやクッションなどを活用してみるとよいでしょう。
寝る前にストレッチを行う
寝る前にストレッチをすると、腰のこりや痛みが和らいで快眠につながるといわれています。また、寝る前のストレッチは硬い床や畳の上などではなく、柔らかい敷布団やマットレスの上で行うことが多いため、安全性が高いといったメリットもあります。寝る前にストレッチをしておくと、睡眠中の寝返りの回数が増えるともいわれています。
- <関連記事>
腰痛には薬で対処することも一つの手
寝方を変えることで腰の負担が軽減される可能性がありますが、原因が寝方だけではない場合には腰痛の改善に繋げることは難しいでしょう。症状がつらいときには、薬を使用することも一つの手です。市販薬で対処する場合は、痛みを和らげる鎮痛成分を配合した内服薬(のみ薬)や湿布などの外用薬があります。また、腰痛の緩和の効能を持つビタミン剤は、痛み止めではありませんが、筋肉や神経の働きに関わるビタミンなどが配合されているため、症状を緩和するために寝方の工夫と共に活用するのもよいでしょう。それぞれについて詳しく解説していきます。
内服薬(のみ薬)
内服薬としては、今起きている痛みを直接的に抑えるための鎮痛剤と、筋肉や神経の疲労回復効果を通じて症状に効いていくビタミンB群やビタミンEを配合したビタミン剤が挙げられます。
・痛みを直接的に抑える鎮痛剤
腰に痛みを感じたときや、痛みがひどいときには、まずは鎮痛剤を使用して痛みを直接的に抑える方法があります。このタイプの薬としては、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やアセトアミノフェンを配合する薬などが該当します。これらの薬は痛みを引き起こす発痛物質(プロスタグランジンなど)の産生を抑制することなどによって、炎症や痛みを抑えるように作用します。痛み止めの内服薬には胃腸障害などの副作用を起こす可能性があるため、説明書をよく読んで服用方法を守ることが大切です。
・筋肉や神経の働きに作用するビタミン剤
ビタミン剤は、鎮痛剤のように直接痛みを止める効果はありませんが、痛みを緩和する効果が期待できます。傷ついた末梢神経の修復に関与し、痛みを和らげるビタミンなどが配合されたビタミン剤を服用するのがおすすめです。
腰痛の緩和が期待できるビタミンとしては、ビタミンB群やビタミンEが挙げられます。
ビタミンB群のなかでも、ビタミンB1は“疲労回復ビタミン”とも呼ばれていて、摂取量が不足してしまうと、筋肉などでエネルギーが十分に作られなくなり、筋肉痛、腰痛などにつながってしまうことがあります。また、ビタミンB1は神経細胞でのエネルギー産生にも関与しています。他にも、ビタミンB6やビタミンB12は神経の機能維持に、ビタミンEは血行促進にかかわっています。これらのビタミンが配合されているビタミン剤を服用することで、腰痛の緩和が期待できます。
- <腰痛の緩和におすすめのアリナミン製品>
外用薬
腰痛に使われる外用薬としては、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などの鎮痛成分を配合している湿布や塗り薬が該当します。これらを使用すると、鎮痛消炎成分が皮膚から患部へ吸収され、炎症が起きている部分に届いて作用し、炎症を抑えて痛みを和らげる効果を発揮します。
つらい腰痛が長引く場合は無理せず医療機関を受診しよう

朝起きたときに腰痛がつらい場合は、睡眠中に腰に負担がかかっているかもしれないので、寝方を工夫してみましょう。腰痛への対処法としては他にも、寝る前にストレッチをしたり、寝具を変えてみたり、筋肉や神経の疲労回復効果が期待できるビタミンを摂ることなども試す価値があります。とはいえ、腰痛にはさまざまな原因がかかわっていることが多いため、これらの対処法を試しても痛みが十分に改善しない場合もあります。また、何か大きな病気が隠れている可能性も。痛みが続く場合や我慢できないほどの痛みが生じている場合は、医師の診察を受けるようにしましょう。
- <参考文献>
- 洋泉社「その腰痛、ほうっておくと脊柱管狭窄症になりますよ。」, 竹谷内 康修, 2017
- さくら舎「脊柱管狭窄症を治す竹谷内式100点法 : ひとつの体操と7つの工夫」, 竹谷内 康修, 2022
- 徳間書店「名医が教える自分で治す脊柱管狭窄症改善トレ」, 竹谷内 康修, 2024
- 宝島社「腰痛を治す本 : あらゆるシーンの痛みに対応!」, 竹谷内 康修, 2013
- 宝島社「腰痛を根本から治す」, 竹谷内 康修, 2013